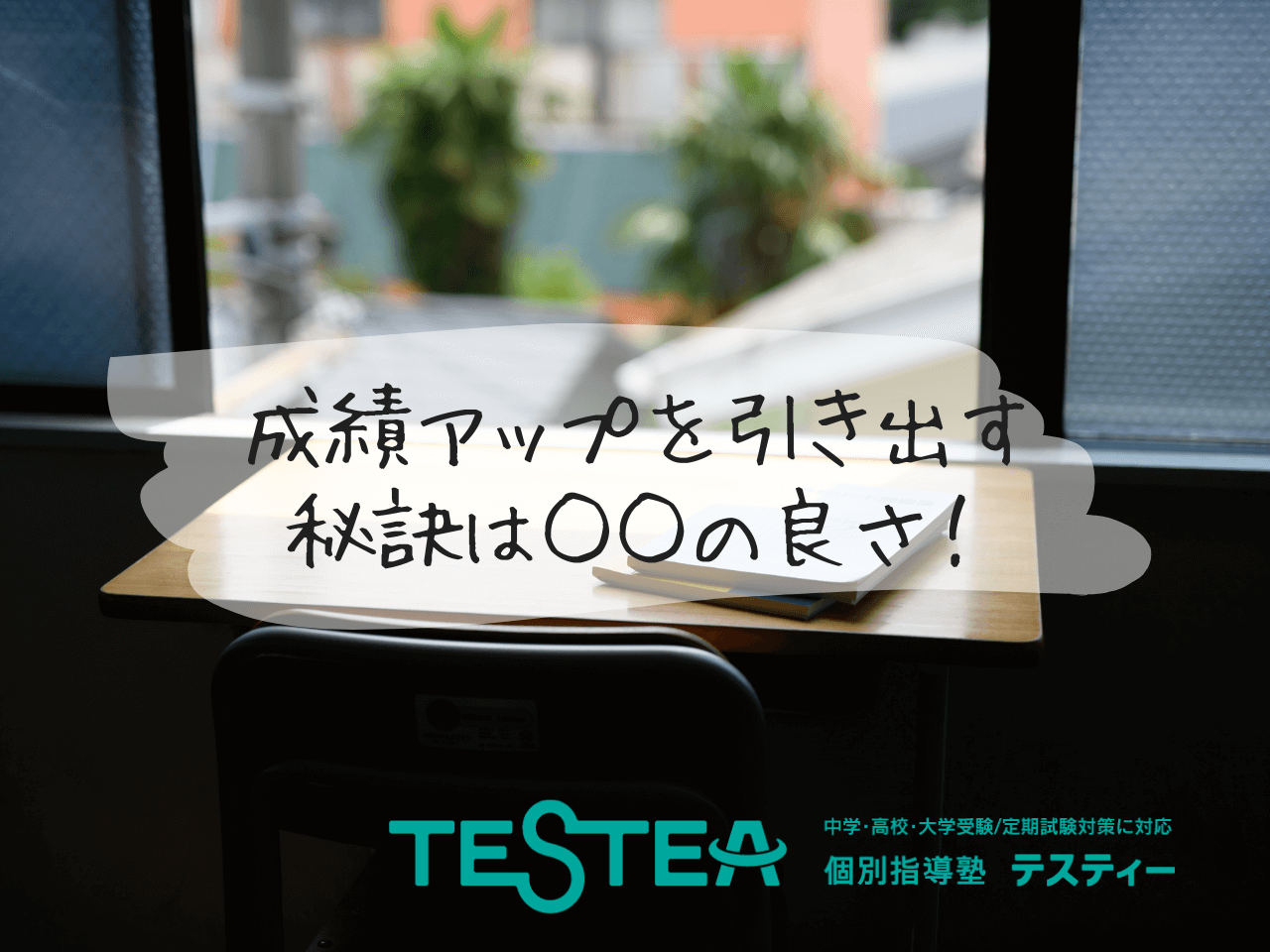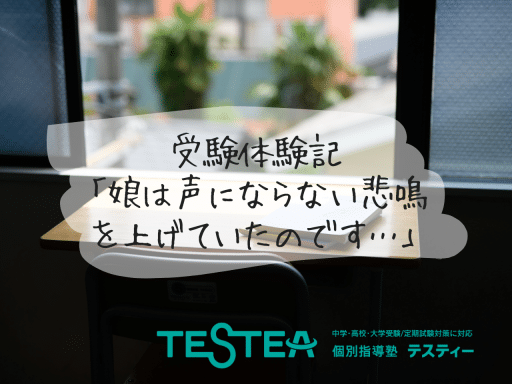勉強を教えるときは子どもの思考の過程を聞いてみよう

こんにちは。
個別指導塾テスティー塾長の繁田和貴です。
みなさんのご家庭では、お子さんがわからない問題は塾で質問できていますか?それとも親御さんが教えていますか?
もし親御さんが教えているとしたら、注意していただきたいことについてお話ししようと思います。
それが今回のタイトルにもなっている「子どもの思考の過程を聞いてみよう」です。
「わからせたつもり」になっていませんか?
以前教えていた生徒で、親から方程式を教えてもらったという子がいました。その子はつるかめ算や差集め算なども方程式で習ったと言って、そのやり方をしようとしていました。しかし、自分で式を立てようとしてもできませんでした。
親に教わったときにはわかったような気がしたけれど、気がしただけだったんですね。いわゆる「わかった”つもり”」というやつです。
塾で習ったやり方もうろ覚え、家で習ったやり方もうろ覚えで、結局どちらも身についていませんでした。
方程式ではないにしても、同じような状態になってしまった生徒は他にも何人もいました。
どうしてこんな中途半端な状態になってしまったのでしょうか?
親がやり方を押しつけると…
その理由は、子どもがどんなやり方を習ったかとか、その問題を解くときにどんな風に考えているかとか、あるいはどこまでわかっているかとかを聞かずに、親が自分のやり方を押しつけてしまったからです。
算数においては、同じ問題に対していろいろな解法があります。
そして、子どもが解法の中の1つを選んで解こうとして、正しい答えまでたどり着けていなかったときには、そのプロセス自体は正しいと伝えて自信を持たせてあげる必要があります。
その後で、できていない続きの部分だけ教えてあげれば、子どもにとっても覚える量は少なくて済みます。
しかし、子どもがどのやり方で解こうとしているかを無視して違うやり方で解説すると、子どもは自分のやり方が間違っていたのかと思ってしまいます。
正しいやり方を、間違っていると思ってしまうのは困りますよね。
子どもの考えを聞くことの大切さ
そして、別のやり方を一から覚えるのも大変です。
ですから、ちゃんと子どもの考えを聞いて、それに合わせて教えてあげる必要があるのです。
塾のテキストやお子さんのノートを見て、先生がどういうやり方で教えているのかを把握しておくことも大事です。
特に4・5年生の子だと、まだ抽象的な数字操作(比でササっと計算)ではなく、具体的な状況を考えてそこから式を立てることが大事だったりもします。
6年生の子だったらこんなやり方させないよな、という遠回りなやり方をあえてすることで原理や法則を実感させることが必要な時期だったりするのです。
下手に解法の先取りをしないようにご注意ください。
まして中学校以降で習う方程式を教えるのはなおさら控えた方が良いです。
xやyを使った文字式を扱う抽象的な思考は、小学生にはなかなか困難です。
特に算数が苦手な子ほど抽象的な思考は苦手ですから数学的な解法は相性が悪いです。
まとめ
お子さんにできないところを教えてあげなければいけないことってありますよね。
でも、そのときに正しい教え方をしないと、かえってお子さんはできなくなってしまうことがあります。
お子さんに算数を教えるときには、今回お伝えした注意点に気を付けてくださいね。
それでは。
関連記事ピックアップ