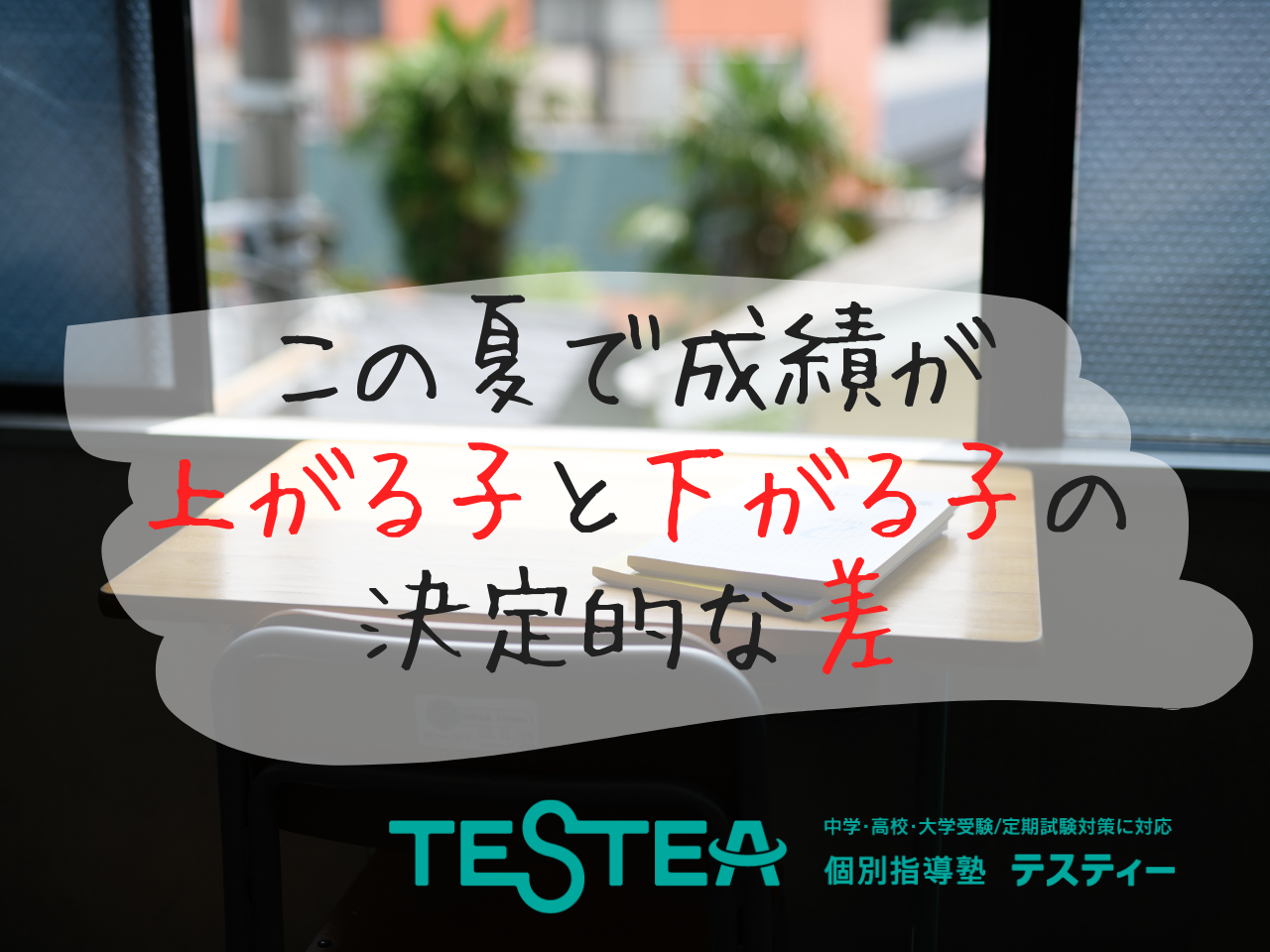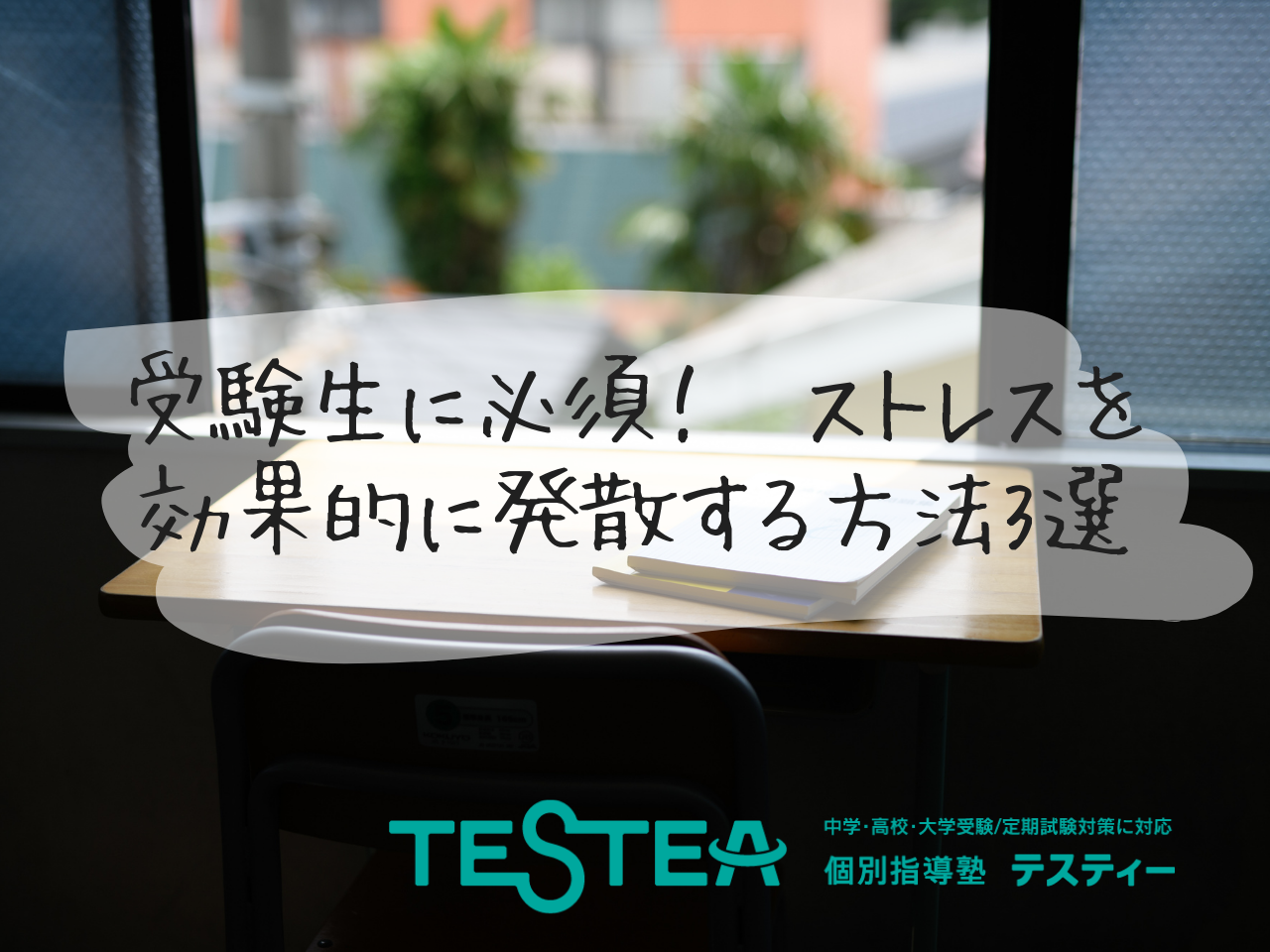やりがちな計算ミスはこうやって減らそう!
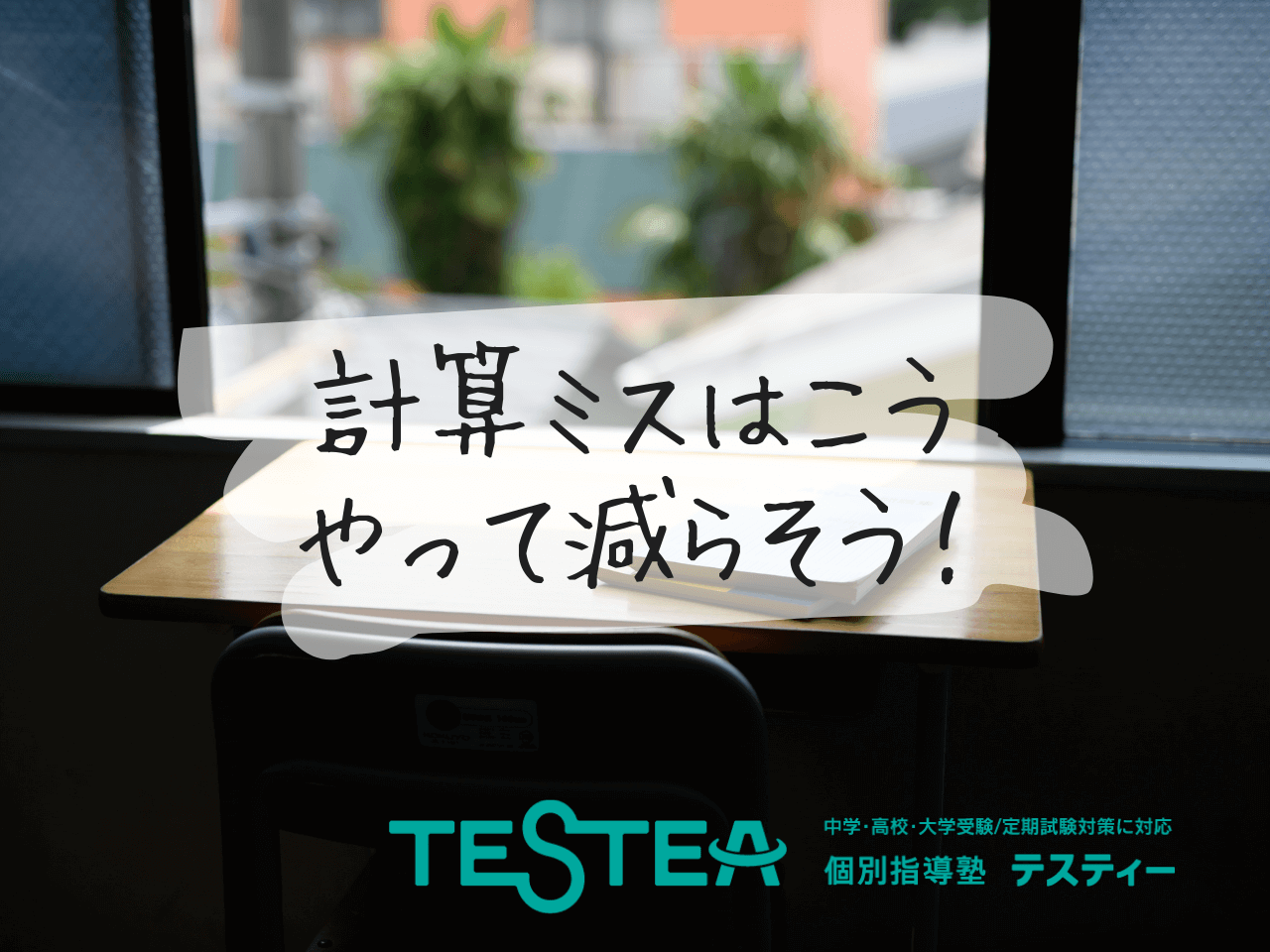
こんにちは。個別指導塾テスティー塾長の繁田和貴です。
計算ミスの重要性
受験シーズン、よく言われることですが、同じくらいの学力の子達が集う入試本番は、合格点前後に何十人も密集します。まさに1ミスが合否を分けます。うっかりミスを減らすことが合格に直結します。
そこで、今回は特に1問当たりの配点の大きい算数で、計算ミスをしない方法について書いてみようと思います。
計算ミスの二大原因
私は計算ミスの原因は大きく分けて2パターンあると思っています。
1. 計算のやり方そのものの習得が不十分
これは単なる実力不足であり、実は「ミス」という表現は適切ではありません。
- 計算の順序を間違いがち
- □に入る数を求める逆算がどうしても苦手
- 繰り上がり・繰り下がりのミスが多い
- 小数の問題で小数点の打ち間違いが多い
- 分数で通分・約分のミスが多い
などなど、一言で計算ミスと言ってもいろいろなパターンがあります。全部を練習していたらキリが無いですね。これらの中でどれが自分に当てはまるかをしっかり特定して絞り込み、そこだけできるようになるまで練習しましょう。
計算問題ではなく文章題・図形問題の途中計算でミスをしたような場合には、「解き直し」よりも「見直し」が大切になります。その問題の解き方自体はわかっていて、もう一度解いたらできたとなっても、計算ミスをしがちという自分の弱点が克服されたわけではないので注意してください。
対策としては、筆算や途中式をちゃんと残し、ミスをしたらどこでつまずいたのかわかるようにしておくとよいでしょう。これは現在5年生以下の子にも当然有効な対策になります。
2. 解き方の理解・定着が不十分
もう1つは、文章題・図形問題の解き方の理解・定着が不十分で、解き方を考えるのに脳のワーキングメモリの大半を持っていかれて、計算に注意を払うだけの余力が無いパターンです。普段だったらありえないようなミスもやらかします。
これを克服するためには、典型問題であれば「うろ覚え」の域を超えて、見たら即解法を思い出せるレベルまで演習を積みましょう。非典型的な(現場思考型)問題であれば、考えていることを図や式に整理して頭の中で考える量を減らすことで、ワーキングメモリの余力を生みましょう。
成長の過程について
「わからない」と「わかる」と「できる」の間にはそれぞれ溝があります。「わかる」に足を踏み入れたばかりの子は、「わかっていたのにできなかった」が頻発するので、点数的には「わからない」だった頃とほとんど変わらないということも多々起こります。
それでも、本人の中ではちゃんと成長があります。そこでくさらず、あきらめずに勉強を続ければ、すぐに「できる」のレベルにたどり着けます。そのためには、数字に表れない成長を、指導者や保護者が気付いて、認め、励まして、あと一歩を後押ししてあげましょう。
最後の対策として
この時期、弱点単元の対策は確かに有効です。ただ、算数はいろいろな単元がありますから、お子さんが苦手な○○算が出題されない可能性はけっこうあります。しかし、計算はどんな問題を解くときにも必ず必要です。ですから、計算ミスを無くす方が、点数アップに直結すると考えることもできるのです。
うちの子は計算ミスが多いなと思うのであれば、ぜひ今から最後の対策として取り組んでみてください。特に今入試を目前に控えている6年生の子は、わかっているはずのことを定着させるために、基本の反復練習に取り組みましょう。その方が新しく何かを覚えようとするより、点数アップして合格に繋がります。
これまで積み重ねてきたものを出し切って、悔いなく受験を終えてくださいね。
それでは!
関連記事ピックアップ