できる子とできない子の決定的な違いとは?
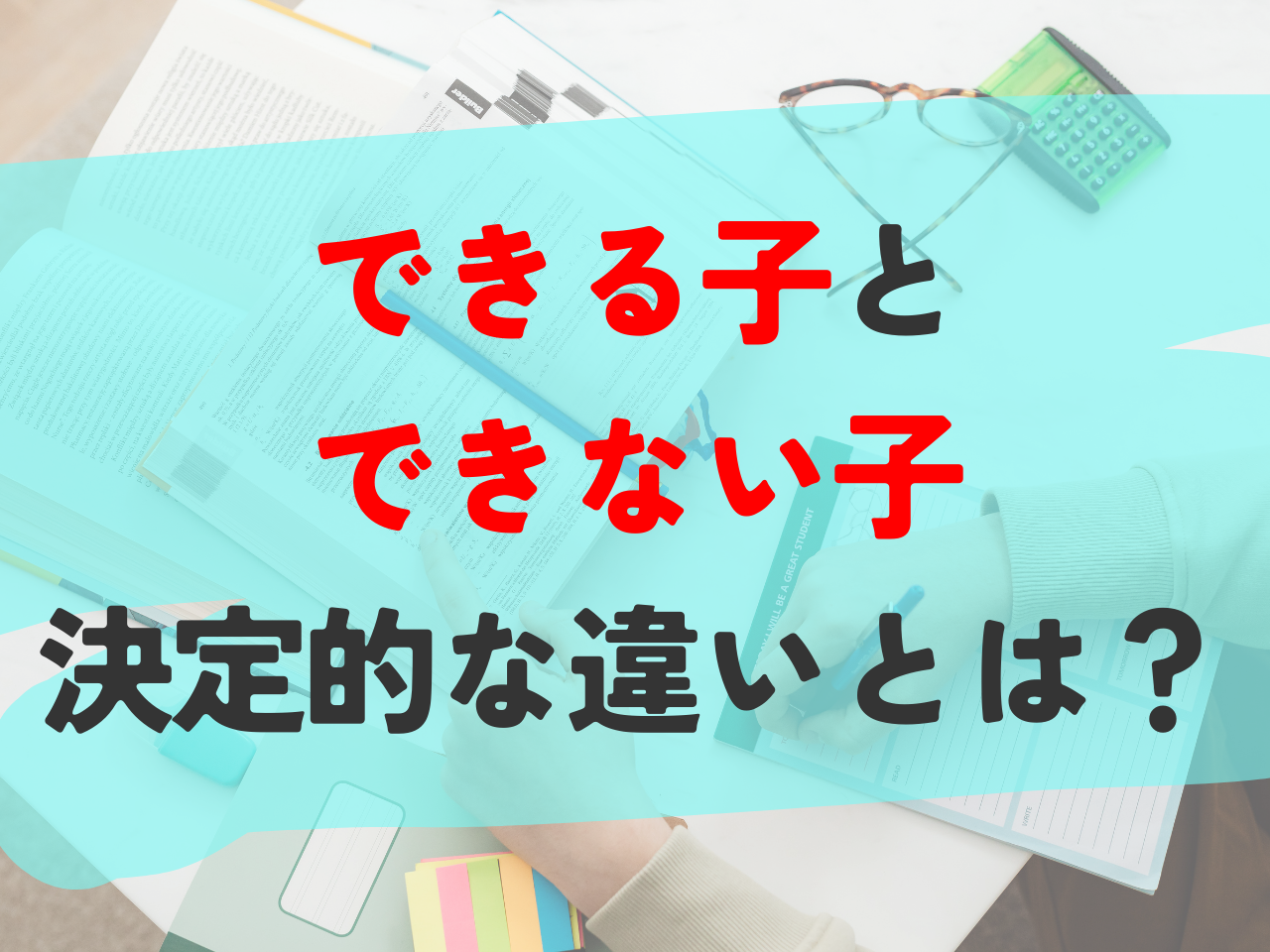
皆さん、こんにちは。
個別指導塾テスティー塾長の繁田和貴です。
最近、早起きが習慣化しつつあります。
当たり前かもしれませんが、
朝から元気に活動すると気持ちいいですね。
以前、医者の友人から、
「気力を高めるには起床時刻を統一することが大事。
睡眠時間が短くなっても、同じ時間に起きることを優先した方がいい」
というアドバイスをもらっていたのですが、
そのアドバイスは確かに正しいと実感しています。
起床時刻を統一することで、睡眠の質もよくなった気がします。
「やろう」と思い立ったのが1月の終わり。
「朝、起きることができないのは、
朝にやることが決まっていないからだ」
という仮説を立てて、
・朝、社員の日報に対してコメントする
・朝8時台にtwitterで1ツイートする
と、朝にやることを決めました。
するとちゃんと起きられるんですね。
早起きでつらいのは起きる瞬間だけで、
エイヤっと起きてしまえば
極端に睡眠時間が短くない限りなんとかなるものです。
そのすぐ後から2月の入試が始まって、
生徒たちの激励のため強制的に毎朝早起きする状態になったのも、
習慣化を後押ししてくれました。
予定や目標があると、
人は行動できるものだなと改めて実感した次第。
行き当たりばったりだと易きに流れるのが人間だよなあ、と。
早起きが当たり前になることで、
見える世界は変わるだろうなあとワクワクしています。
これって、子どもの勉強でも同じですよね。
予定や目標を決めておかないと、
勉強の効率が上がらなかったり、
そもそも勉強に着手できなかったりするものです。
だからまずは小さなところから、
例えば明日の予定を決めるとか、
計算ドリルの目標点数を決めるとか、
そういったところから始めてみましょう。
多くの中学受験塾は2月から新学年に切り替わり、
通塾回数や通塾曜日が変更になったことと思います。
今年から塾通いを始めようとしている人もいるでしょう。
1週間のスケジュールが切り替わるこのタイミングは、
一念発起して今までの当たり前の基準を変えるチャンスです。
やることを決めておくのが当たり前、
目標を立てるのが当たり前。
今はそんな意識改革をしやすい時期だと言えます。
まずは1日単位の予定決めから始めて、
やがて1週間の理想的な予定(スケジュール)決めに発展させていきましょう。
少しずつ行動が変わり、成果につながっていくはずです。
これはもちろん、
中学受験が終わりたての6年生についても言えることです。
ほとんどの生徒は通塾回数が減るなど、
受験前とは違ったスケジュールになっていると思います。
まあ、楽なスケジュールになっているわけですよね。
何も考えずに日々過ごしていれば、
中学に入学する頃にはおそらく勉強の体力が
限りなくゼロに近くなっているでしょう。
中学受験でせっかく身についた勉強習慣が消滅してしまいます。
一方で、
「算数は苦手だったけど数学は得意にする!そのために○○をする」とか、
「英語を圧倒的な得意教科にする!入学前に○○まで終わらせよう」のように、
きちんと目標を定め、予定を立てて頑張った人は、
それまでの勉強の苦手意識を一気に払拭することも可能です。
というのも、中学に入って最初の定期試験の数学や英語の内容は、
実はそんなに難しいものではないのです。
少なくとも中学受験の終盤でやっていた内容の方がよっぽど高度です。
だからちゃんとやりさえすれば、満点に近い点数を取ることだってできます。
そうなれば勉強におけるセルフイメージはぐんと向上しますよね。
勉強がデキるのが「当たり前」になることだって夢ではありません。
「今年は当たり前の基準を変えていきたい」
と自分の決意表明をしましたが、
皆さんとお子さんも、
一緒に当たり前の基準を変えていきませんか?
意識の当たり前を変える。
行動の当たり前を変える。
そのためにはまず、予定と目標を立てるところからです。
別に失敗したっていいんです。
「週4以上で約2か月間継続」すれば、習慣化につながります。
週に3回までは予定通りにいかなくてもいいと思えば気が楽ですよね。
これは決して、昨晩ついつい飲みすぎてしまい、
今朝10時起きだった自分を慰めているわけではありません(笑)
深酒&遅起きはやっぱり体が重いなあと痛感したので、
この反省を明日以降に活かせばよいと思っています。
繰り返しますが、新学年は今までの習慣を変える大チャンスです。
習慣の違いが成果・成長の違いになります。
ぜひ一緒により良い「当たり前」、作っていきましょうね。
それでは!


