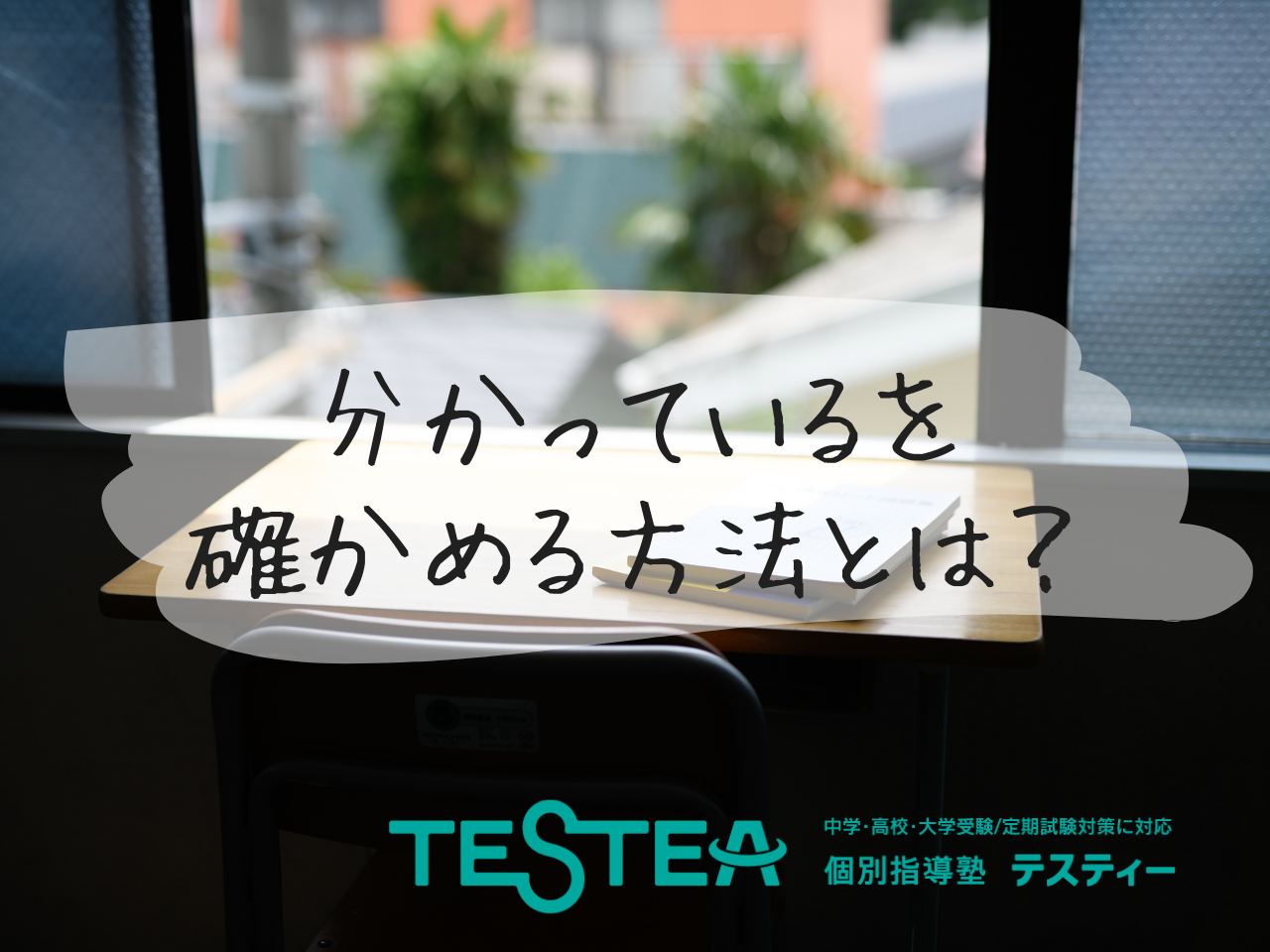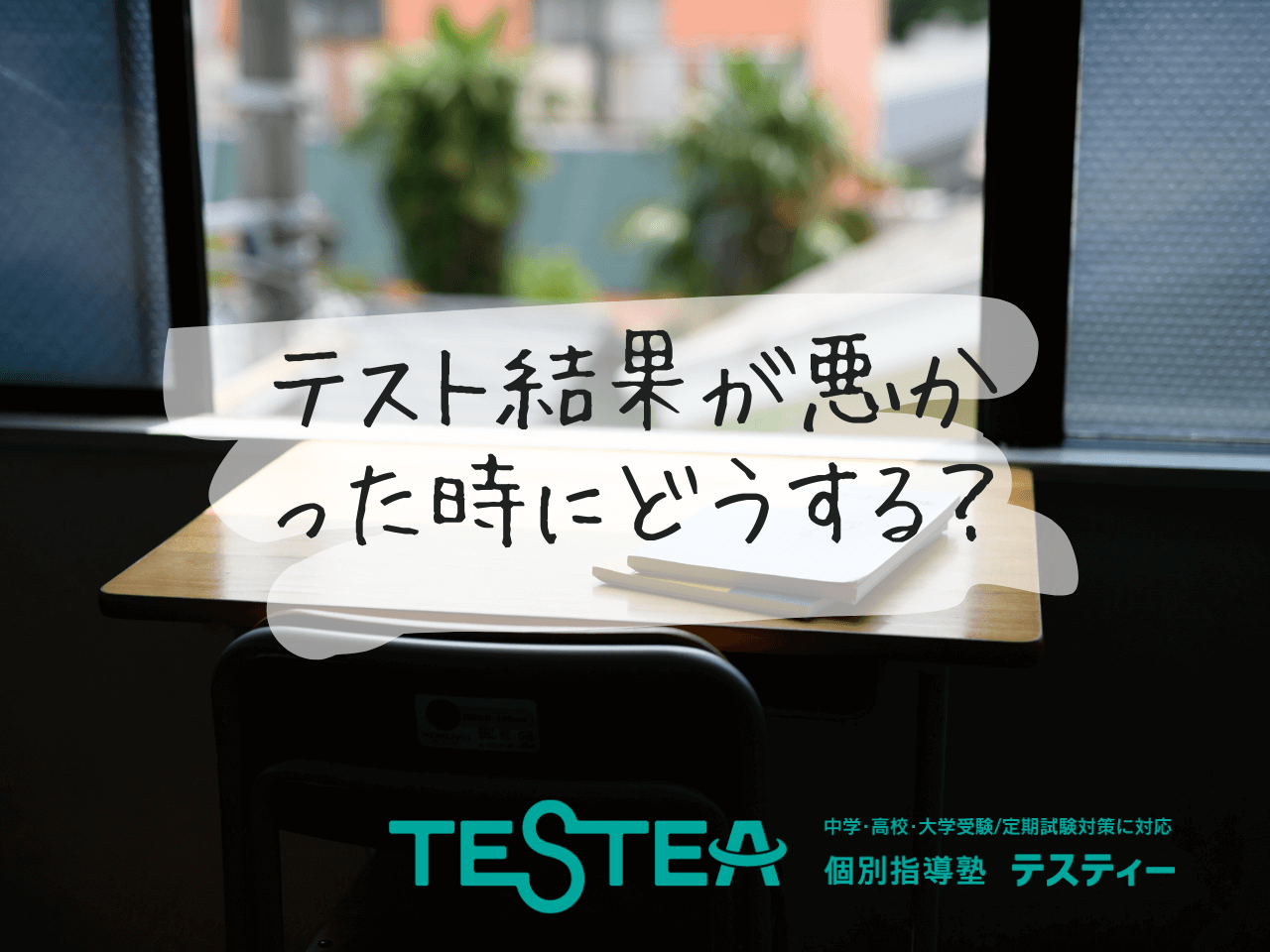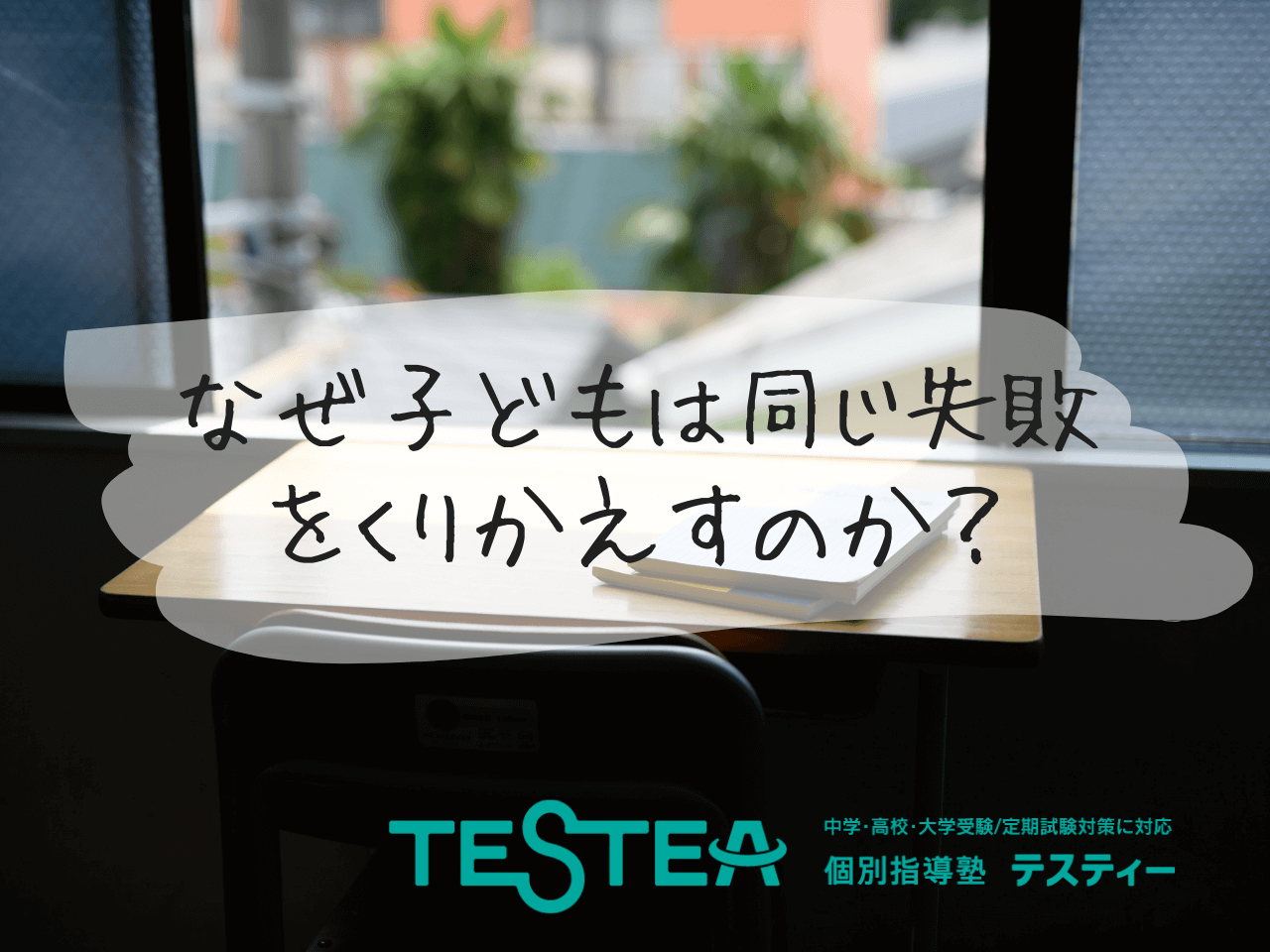子どもの「分かっている」を確かめる方法とは?
こんにちは。
テスティーの繁田です。
ここ最近、画面越しではありますが算数道場を通じてたくさんの生徒を指導する機会がありました。
この数年は経営にまつわる業務が増えていましたが、やっぱり直接指導するのは楽しいですね。
数は少ないですが、個別の授業もしています。
今日は私が授業をしているときに心がけているポイントについてシェアしたいと思います。
教室での対面授業でもオンライン授業でも、共通して言える大切なポイントです。
テスティーで他の講師たちにも徹底させている、成績アップのヒケツですので、ご家庭でもぜひ役立ててください。
子どもの成績が上がらない理由
子どもの成績が上がらない理由はいろいろありますが、なかでもありがちなのが、わかっていないのに授業が進んでいってしまうことです。
まだよくわかっていないけど恥ずかしくてそれを言えない、とか、馬鹿だと思われるのが怖くて質問できない、とか。
あるいは、わかったつもりになっているけど、本当はまだわかっていないなんて場合もありますね。
いずれのケースでも、指導をする側がわかっていないことに気づいて、わかるまで教えてあげることが必要です。
特に「わかったつもり」が多い子の場合には、正しい「わかった」の感覚を身につけさせてあげなければいけません。
なぜなら、家庭学習のときにも「わからない」問題を放置することになってしまうので、ますます成績ダウンにつながってしまうからです。
子どもがわかっているかどうかを確認する方法
では、子どもがわかっているかどうかを確認するためにはどうすれば良いでしょうか?
一般的なのは「わかった?」と問いかけて確認することですが、この方法は実は効果が低いです。
なぜなら「わかりました!」という返事は、わかっていなくてもできるからです。私も生徒の「わかりました」に何度だまされて悲しい思いをしたことか……
生徒の側にも悪気は無かったりしますから(わかったつもり)、責めることもできないのですが、成績アップのためにはこれではいけませんね。
本当にわかったかどうかを確認する方法の原則はシンプルです。
「わかっていなければできないことをさせる」
これです。
「わかった」を確認する具体例
例えば、「なにがわかったのか、わかったことを説明させる」といったことです。
ある算数の問題の解き方がわかったかどうかを確認したければ、
- どんなときにその解き方を使うと便利なのか
- なぜその解き方で答えが求められるのか
- 他の解法との違いは何なのか
といったことを説明してもらいましょう。
他にも例えば「類題や周辺知識を聞いてみる」というのも良いですね。
理科で「二酸化炭素と水を原料に光のエネルギーを使ってでんぷんを作る働きは?」「光合成」がわかったかを確認したければ、「光合成ででんぷんを作る際の原料を2つあげよ」「二酸化炭素と水」という風に逆から聞いてみるとか。
わからないところを放置せずに、わかるまでやるようにすれば、成績アップは意外と簡単です。
みなさんのお子さんにも、正しい「わかった」の感覚を身につけさせてあげてくださいね。
そのための方法として、「わかっていなければできないことをさせる」をぜひやっていってください。
ただし、やりすぎると親子げんかになるのでご注意を!
それではまた!
関連記事ピックアップ